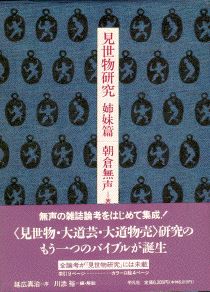
『朝倉無声 見世物研究姉妹篇』解説
川添裕
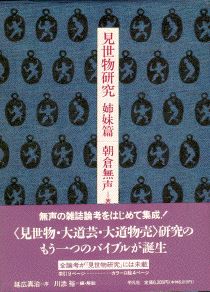
成り立ち
『朝倉無声 見世物研究姉妹篇』は、江戸文化史研究の先駆者として知られる朝倉無声(明治一〇年−昭和二年)の雑誌論考のなかから、見世物・大道芸・大道物売に関するものを集成し、はじめて一書にまとめたものである。
朝倉無声には周知のように『見世物研究』(昭和三年、春陽堂刊)の書があり、今日不朽の名著の評価を得てこの分野でのバイブル的存在となっているが、本書に収録の論考はすべてがこの『見世物研究』には未載であり、単行書のかたちでは、はじめて人目にふれる内容となる。もちろん、掲載の元雑誌に当たればそれらを目にすることは可能だが、巻末に掲げた「初出一覧」[現行のウェブ版には未掲載]からもわかるように、その掲載誌が明治末から大正前期にかけて刊行された宮武外骨編集の『此花』や、無声編集の『此花』『風俗図説』『江戸趣味』また『浮世絵』といった、いずれも今では稀覯に属するものであり、大規模な図書館ですらすべてを完備する例が少ないことを考えるならば、はじめて公にされるという言い方も、あながち誇張とはいえまい。
しかし、もっと重要なことは、これらの論考が先の『見世物研究』の内容を補完し、かつまた「番い」をなすような関係にあることである。本書に敢えて『見世物研究姉妹篇』の名を付した理由もそこにあるが、編者としては、無声が残した仕事の足跡を追う年来の試みのなかで、もしわれわれが無声の見世物・大道芸研究全体の展望を得ようとするなら、『見世物研究』一書のみでは決して充分でなく、是非とも本書に盛られた内容の出版が併せて必要と考え、上梓に至った次第である。
まだ若くして世を去った無声がいま少し長生すれば、『見世物研究』に続いて本書に相当する書が上梓された可能性もあり得るのではないか−−じつは私はそんな推測をしているのだが、しかし現実は名著『見世物研究』さえが、かれの没後一年を経てからの出版となった。そしてこの『見世物研究』に関しては、没後の出版となったがゆえの若干の構成上の不備(無声自身が目を通していればそうはならなかったであろうような不備)のあることが、同書の復刻版(昭和五二年、思文閣出版)の解題執筆者、守屋毅氏によってすでに指摘されている。そのため守屋氏は、本来なら収録されてしかるべき、あるいは収録されることが望ましい二篇の論考(「辻放下と豆蔵」「生人形の話」)を新たに補遺のかたちで加え、復刻版に収録している。
本書の内容は、ある意味でそうした補遺を大規模に発展させたものともいえるが、しかしそれだけにとどまらず、他の大道の諸芸能や大道物売等の隣接分野をも積極的に包含することで、元来かなり大きな見通しのもとに構想されたと思われる無声のこの分野での仕事の全貌を、できるだけ再現しようと試みたものである。
この新たな書が、はたしてもう一つのバイブルたり得るのか、その答えは基本的に読者に委ねたいと思っているが、編者としてはともかくこの書が広く利用されることを願いつつ、以下、本書の内容と構成、また個別の論考に即して幾つかの問題にふれ、最後に研究の動向を記すことで、『見世物研究姉妹篇』の解説としたい。なお、表記・校訂等の方針に関しては、巻頭の「凡例」[現行のウェブ版には未掲載]をご参照いただきたい。
内容と構成
ここには、全部で五九篇の論考が収録されている。原題と初出は、巻末の「初出一覧」の通りである。ただし収録にあたっては、上・中・下等のかたちで分載されたものはすべて一本にまとめ、連載物には一定の順序数を付して一括して掲載した。したがって本書では、五九篇の論考が最終的に二六章の体裁で掲載されている。発表の年月でいうと、最も古いものが明治四四年三月、最も新しいものが大正八年三月の発表で、無声の三十代半ばから四十代はじめにかけての約八年間に、系統的・意識的・集中的に書かれたものの集成といえる。
本書ではこれらの論考を、
1 見世物篇
2 大道芸・諸芸篇
3 大道物売篇
の三部に分けて編集した。各篇内での順序は、原則として発表の時代順としている。「見世物」「大道芸」「大道物売」の区分は、通行のおおまかな基準にしたがって行なったもので、1の見世物篇は、いわば『見世物研究』の直接的な補遺としての性格も持つパート、2の大道芸・諸芸篇および3の大道物売篇が、これまで無声の仕事としてあまり焦点をあてられることのなかった、隣接のジャンルということになる。
ただ、ここでやや自己矛盾に陥ることを承知で言っておけば、この三部構成は、基本的には五九篇の論考をスムースに構成するための便宜上の工夫であって、こうした分類そのものに必要以上の価値を認めているわけではない。むしろ、本書の意図するところは、今日『見世物研究』の記述だけが無声のこの分野での仕事として孤高を誇る結果となっているが、実際にはその研究は「見世物−大道芸−大道物売」という連鎖する世界の全体を見据えたうえで、同時並行的、同時多発的に行われたものであり、そうした無声の世界をそのままに、いってみれば「三位一体」のかたちで統合的に示そうとしたことにある。
考えてみれば、「見世物」と「大道芸」の区別といっても、多くの一般の人びとにとっては漠然と相似た雑芸の類と意識されているのが実情だろう。各種の事典類では、大道や辻々の野天で行われる簡素な雑芸が「大道芸」であるのに対し、小屋掛けで興行される雑芸が「見世物」といった風に、野天か小屋掛けかの興行場所の違いから両者を説明するが、それは場所という興行の一局面からのみとらえた場合の限定的な分類であって、芸態や芸人集団、あるいはその社会的地位や文化的意味合いなどを含んだうえでの、根底的な区別とはなっていない。また「見世物」という言葉自体は、何かを人目にさらす、さらしものにするといった意味合いで、分類用語とは異なるより広い文脈で用いられることにも注意する必要があるだろう。筆者自身は区別の視点として、それぞれに関わる職能集団−−香具師、乞胸と、非人、また願人−−の違いから、集団間の対抗・提携関係をも含めて、一定の区別が可能との見通しを持っているが、ここではそのことよりも、表現としての見世物、大道芸、大道物売が、歴史的・伝統的に「相並ぶもの」「同類のもの」「重なり合うもの」として存在し、人びとに意識されてきたという事実に注目しておきたい。
そのさい、まず確認しておかなければならないのは、江戸時代後期の見世物、大道芸、大道物売の一定部分が、香具師と呼ばれる集団によって担われ、あるいは管掌されてきたという歴史的事実である。香具師の職掌として通常あげられるのは、いわゆる「十三香具」と呼ばれるもので、その「十三」の内容は史料によって必ずしも一定しないが、例えば寛政八年(一七九六)に、香具師と乞胸集団とのあいだでその職掌の範囲をめぐって係争がおこったさい、香具師たちが奉行所に提出した文書では、居合抜・曲鞠・唄廻し・軽業・見世物・覗・懐中掛香売・諸国広商人・辻療治膏薬売・蜜柑梨子砂糖漬売・小間物売・火打保口売・諸国妙薬取次売の十三を、自分たちの昔からの生業としてあげている。こうしてみると本書におさめた論考の多くが、何らかの意味でこれら「十三香具」の系流にあることがご理解いただけると思う。なお、ここで問題の乞胸は、本書の三部構成のなかでいう「大道芸」系の芸能を中心に、見世物の一定部分と、門付芸を中心的な生計手段としてきた別個の職能集団だが、ここでの香具師との争いが如実に示しているように、きわめて職掌の近接する、重なり合う部分を持った集団であり、この分野の研究では当然同一視野におさめるべきものといえる。
つまりこうしてみると、無声はきわめて自然の成り行きとして、見世物、大道芸、大道物売をあるがままに基本的に「一体」のものとしてとらえ、そのなかで旺盛な個別研究を展開したのであり、そうした一連の研究を集成した結果が、本書ということになろう。
さて、大分前置きが長くなってしまったが、以下、収録の論考を具体的にとりあげて、解説を加えることにしよう。ただ、あらかじめお断りしておかなければならないのは、無声の身ならぬ編者には、とうてい全論考について解説を加えるだけの能力はない。元来、無声の仕事そのものにふれることが本書の趣旨とご理解いただいて、ここでは若干の解説と必要最小限の注釈のみ施すことで、お許しをいただきたいと思う。
1 見世物篇
まず、見世物篇は「江戸菊細工の変遷」ではじまる。菊細工のはきわめて貴重なものであり、しかも冒頭の、菊細工の起源を、諸書を渉猟しながらその記述の微妙な違いから見きわめていく手際には、博捜の考証家無声らしさが横溢している。小さな植物に豊かな想像力を躍動させた菊細工は、朝顔や万年青の栽培と同様、いかにもミクロコスモスに生きる江戸の人びとらしい楽しみであったが、文化期から大正の改元にまでおよぶ無声の記述は、こうした一つの江戸文化の誕生と終焉をよく教えてくれるもので、本書の巻頭を飾るにふさわしい論考といえよう。
次の「見世物年代記」に関しては、やや複雑な説明が必要である。じつはこの「見世物年代記」こそ、無声の見世物研究における根本資料集というべきもので、その内容は、博捜の文献から抜き書きにした見世物関係記事を、寛永年間から幕末(・明治)にいたるまで年代順に編集したものである。その大部の稿本は、すでに大正の早い時点でほぼ完成していたものと推測されるが、不幸なことに今日にいたるまで公刊されることがなく、完全なかたちでの稿本(一六巻本または一七巻本)は行方知れずとなっている(なお、別本一四巻本は国立国会図書館支部東洋文庫蔵)。ところが、ここに見るように、その一部は無声編集の『此花』に付録として掲載されていたのである。本書のページ数にしてわずか一二ページ、記述も万治年間の『今様都踊くどき』の途中で中途半端に終わっていて、全体からみるとごくわずかな部分でしかないのが、しかし、ともかく無声自身の手により公にされたという点で、稿本とはまた異なる価値を持つといえる。なお、本文を東洋文庫蔵一四巻本と比較すると、大差は見られぬが幾つかの小異が確認される。
本書に収録の論考がすべて単行本未収録であることは、すでにはじめにふれたとおりだが、「駱駝の見世物」のかぎっては『見世物研究』所載の記事と内容的に重複するところが多い。執筆の経緯でいえば、先に書かれたこの「駱駝の見世物」の記事を基に、文体を平易に改めるといった程度の変更で『見世物研究』の記事を綴ったものと思われるが、ただ、そのさいどういうわけか、天保四年(一八三三)春の江戸への駱駝再来の記述が省かれている。無声が典拠とした『巷街贅説』には、たしかに当該記事が確認され、したがってこの省略が単なる遺漏により生じたのか、あるいは訂正等何らかの意思に基づくものなのか現時点では判断しかねるが、そうした問題提起の意味もこめて、この論考を掲載した次第である。なお、ここでふれている江戸における駱駝の興行年時を、文政四年(一八二一)と記す例を多く見かけるが、これは同じ駱駝の長崎への渡来年と混同したもので、江戸での興行は文政七年(一八二四)閏八月からのことである。恐らくこの誤りは、同様の混同がみられる『武江年表』記事にのみ拠るところから生じたものと思われるが、そうした誤解をとく際にも、無声の考証は一定の価値を持つ。
2 大道芸・諸芸篇
大道芸・諸芸篇に収められた一四篇の論考も、「あはしま」といい「まかしよとわいわい天王」といい「節季候と婆等」といい、いずれも他に例のない貴重な研究である。また、先にふれたように「十三香具師考」は、この分野全体の見取図を描くうえでも見過しにできない研究である。これら大道芸人・門付芸人たちが見せた芸は、パフォーマンスとして見れば、ほとんど芸ともいえないような他愛のないものもあり、そうしたささやかな芸をもって身すぎ世すぎの手段とせざるを得なかった社会的現実にも、私たちは目を向けていかなければならないが、その、ときに途方途轍もない芸の発想をみていると、日常世界の「常識」の限界をむしろ補完するような、別種の「理」の存在に率直に思いを致さざるを得ない。
もう一つ、ここで注目しておきたい論考に「智多万歳に就て」がある。智多万歳(そしていわゆる「三河万歳」「尾張万歳」)に関しては、近年、山路興造氏の優れた研究によってその起源と成立事情が明らかにされつつあり、京都から尾張に強制的に移住させられた千秋万歳(声聞師、陰陽師)が、その発祥に深く関わりのあったことが指摘されている(山路興造「萬歳の成立」『民俗芸能研究』八号、一九八八。のち『翁の座』、平凡社、一九九一に収録)。無声の研究はもとより断片的なもので、山路氏の探究に及ぶものではないが、ただそこにある芽は同じ方向を目指したものであり、しかも「予は数年以前から、万歳考編述の為に、諸国に於ける万歳の由緒風俗歌章等を、極力蒐集してゐる」といった記述を読むと、つくづくその関心の早さと、目のつけどころの良さに感心せざるを得ない。ここにいう「万歳考」が無声自身によって著される機会は永久に失われてしまったが、しかしその種子がまかれ、現に「智多万歳に就て」のなかに芽生えていることは、今後の研究への一つの礎として受けとめておきたいと思う。
なお、この大道芸・諸芸篇は表題の通り、いわゆる「大道芸」のパート(「智多萬歳に就て」までの一〇篇)と、「諸芸」のパート(残り四篇)の二つからなっている。ここにいう「諸芸」とは、いうまでもなく積極的な分類ではなく、むしろ分類しがたいその他の芸能をまとめたものに過ぎない。その内容は、芝居小屋の周辺芸能から、寄席演芸的なもの、また吉原俄などと雑多だが、これもまた構成上の便宜的なものとしてご理解いただければと思う。
3 大道物売篇
大道物売篇の一連の論考は、多くが連載のかたちで掲載されていたことにも示されるように、無声が力を入れて系統的に研究を展開した分野である。
ここで注目しておきたいのは、例えば「お万飴売」や「朝鮮弘慶子薬売」といった論考である。肥満の大男が女装して飴を売り歩いたお万飴売といい、竹の子笠をかぶり朝鮮人風の格好で薬を売り歩いた朝鮮弘慶子といい、単なる物売というよりも、それ自体がきわめて芸能的な存在であったことは、本文を見ればすぐにおわかりいただけると思うが、さらに興味深いことは、こうした大道の芸能・風俗が歌舞伎に取り入れられ、舞台の上でも演じられて大いに評判を呼んだ点である。例えば、お万飴売は天保一〇年(一八三九)、中村座春狂言大切所作事に中村歌右衛門が演じて大当りとなり、朝鮮弘慶子は安永期に、当時の道外方の嵐音八が扮して好評を博したことを無声は記している。そして、お万飴売の場合、この大入りにより歌右衛門から仕着を遣わされ、そのことがまた評判となって、ますます繁盛したと付け加えている。
ここにみるような大道の芸能・風俗と歌舞伎とのあいだの、互いが互いを反映し合うような関係は、両者が興行上の地位のうえでの区別を持ちながら、その一方で、「根」のレベルにおいては同一の地平にあることを示唆しているとともに、それがまた実利を生み出す論理で結ばれている点に、いかにも芸能ならではの特質をみてとることができる。歌舞伎のように、現在ではひとつの自己完結したジャンルのように思われがちな芸能にしても、実際には、見世物、大道芸、大道物売などと「一体」のものとしてとらえる視点ぬきには見えてこない多くの興味深い特徴をそなえており、そうした大道の芸能・風俗との豊かな交流は、落語や講談などの庶民芸能についていえば、より色濃く見てとることのできるものであった。また、歌舞伎における講釈ダネの多さをも視野に入れるなら、結局、これら芸能の関係の基本は、上(歌舞伎)から下(寄席芸・雑芸)への普及などという単純な図式ではなく、リフレクシヴな相補的な関係であり、その視点抜きには、大衆の文化の本質は見えてこない。
そしてさらに、これら諸芸能が、互いの共鳴し合う関係のなかに表現の場や表現のかたちを見出だしていくあり方は、その延長線上に風俗絵画としての浮世絵の世界をも巻き込んでいる。歌舞伎と役者絵のあいだの相互刺激的な共存共栄の関係については、つとに鈴木重三氏、服部幸雄氏が指摘しているところだが、同じように大道の芸能・風俗や見世物も、しばしば浮世絵や風俗絵本、小説挿絵類に描かれてさらなる庶民の話題となり、当事者、版元の双方に、現実的な利益をもたらした。先の歌舞伎に取り入れられた二つの大道物売にしても、朝鮮弘慶子は北斎(春朗)により、お万飴売は国芳により描かれて、浮世絵として板行されたことが知られるが、こうした話題の芸能・風俗の絵画化は、それを身近に手にとって見たいという庶民の欲求に、巧みにかたちを与えるものであった。これまで浮世絵研究の世界では、こうした類の作品への位置づけが適切に行われているとはいえず、無声の一連の研究は、その意味からも大いに注目して欲しい仕事といえる。
なお、この大道物売篇中の「牙婆考」および「香具若衆考」の論考は、売色との関わりを持つ点で他とやや性格を異にしている。それゆえここでは末尾に置くこととしたが、ただ本質的な問題でいえば、こうした売色もまた芸能世界や大道物売と交差するところのものであり、無声自身もその方面での研究を多く残している。ここでは編集方針の都合上、それらすべてを収録することはしなかったが、そうした「視点」だけは残しておきたいがために、大道物売篇として違和感のない二篇にかぎって紹介した次第である。
3 研究の動向
(以下、略。改訂準備中)